この本で得られる学び
- 勝てるデザインとは何か?
- 勝てるデザインが持つ5つの要素
- どうすれば勝てるデザインを実現できるか?
勝てるデザインとは何か?
著者は本書をこう語る。
「勝てるデザイン」より引用
僕がこれまで本気で一流のデザイナーを目指し、インプットし、任天堂で仕事を実践しながら生まれた「仕事術とデザイン力」のすべて。
任天堂を退社後、フリーランスという荒野で、そして起業してから実践した結果のすべて。
(中略)
僕が書いたものは、あくまで凡人ならではの等身大で正直でリアルな「デザイン」です。
一般的にデザインは問題解決であるといわれているが、著者は単に問題を解決するのではなく、興味を奪うデザインで心動かすことでそれを実践している。
著者は、本書での「勝てるデザイン」を、「企画して人が喜ぶものを、人の心を動かすものを。」と定義している。
勝てるデザインが持つ5つの要素
著者は勝てるデザインに求められる条件を、次の5つに整理している。
- 一撃でわかるデザイン
たくさんの情報量を一撃で伝えられるデザイン(情報バズーカ)であること。デザインの質は思考量と必ず比例するので、プレゼンができるくらい深く考えることが重要である。 - ポリシーがあるデザイン
企画内容やデザインの世界観などの大事にすること(コンセプト、印ろう)を明確にして、それをブレずに守り抜くこと。 - ならではのデザイン
他の誰でもない、「あなた」や「そのクライアント」だからこそ成立するデザイン。クライアントA向けのデザインが、別のクライアントBに対してもまるまる転用できるのであれば、それは、ならではのデザインとは言えない。 - 興味を奪うデザイン
埋もれてしまわない、「無視できない何か」をもったデザインであること。美しく、かっこいいデザインはたくさんあふれているため、それだけでは不十分である。 - 捨てられないデザイン
部屋に飾っておきたくなるようなクオリティの高いデザインであること。
どうすれば勝てるデザインを実現できるか?
本書では、「勝てるデザイン」を実現するための具体的な手法や思考法、心構えが数多く紹介されている。その中から、特に印象的だったポイントを3つ取り上げて紹介したい。
- 企画の段階では、何人を幸せにできるか?を考える
著者はデザイナーが単なる「外注の実行者」にとどまっていては、心を動かす仕事にはならないと語る。では、その「自分の企画」として考えるべき企画とは、どのようなものなのか。
その答えが「幸せになる人の数が多い企画」である。
「勝てるデザイン」とは、人の心を動かし、喜びを生み出すものであり、それを実現する企画とは、多くの人の幸せにつながる設計でなければならない。 - デザインの必殺技を増やす
デザイン力を高めるうえで重要なのが、「必殺技」を自らの中に蓄積しておくことだと著者は語る。ここでいう必殺技とは、他人の優れたデザインやアイデアから得た“エッセンス”を、自分なりに言語化し、ストックとして使えるようにしたものだ。
単に「よさそう」と感じた表現を真似るのではなく、「なぜそれが良いと感じたのか?」「それによってどんな効果が生まれるのか?」を明確にし、整理しておく。この習慣が、状況に応じた適切なデザイン選択を可能にする、実践的な引き出しとなる。
たとえば、著者が実際にストックしている「必殺技」の例には以下のようなものがある。
・ドラマチック事件
モノクロの写真に赤文字を重ねることで、かっこよくニュース性を演出できる。
・ピコピコメモリーズ
ドット絵でゲームを連想させ、昔の懐かしい、楽しい思い出を想起させる効果がある。
著者はこの引き出しを、自らの圧倒的なインプットによって築いてきた。デザイン書の棚を端から端まで読み込み、網羅的に知識と表現を吸収してきたという。その姿勢がうかがえる印象的な一節がこちらだ。
本具体的にはまず、デザインの本を読みまくりました。
本当に、和洋問わず、書店のデザインコーナーの棚の端から端まで、ありとあらゆるデザイン関連の書籍を読んでいきました。
「勝てるデザイン」より引用
(中略)
で、そういう話をすると若いデザイナーからは当然のごとく、「おすすめの本はありますか?」と聞かれます。一応優しく何冊か教えるんだけれど、本音では、「興味があるなら、すべて目を通すでしょ?」と思っています。
(中略)
何かを極めたい時に、良いものだけを吸収したいという人からは、情熱を感じません。
この言葉には、「本気で取り組みたいことなら、他人に近道を聞くのではなく、自ら手と足を動かして情報に当たるべきだ」というメッセージが込められている。そしてそれは、なにもデザインに限った話ではない。学びの本質や、情熱のあり方にまで踏み込んだ本質的な指摘として、読者に深い気づきを与えてくれる一節である。
- デザインする前にプレゼンを考えよ
実際にデザインに取りかかる前に、「どう伝えるか?」を考えることが重要だと著者は説く。
これは単なる作業手順の話ではない。ものづくりの根幹に関わる姿勢であり、たとえばAmazonでは新しい製品やサービスを立ち上げる際、最初に“プレスリリース”を書くという文化がある。つまり、「なぜこのプロダクトが存在するのか?」をあらかじめ言語化し、そこから逆算して開発を進めるという手法だ。
このように先に伝えることを想定することで、デザインの方向性や狙いがぶれにくくなる。
その際に特に有効なのが、「コンセプト=印ろう」という視点である。
「なぜこの形なのか?」「なぜこの色なのか?」と問われたときに、一発で納得させられるだけの説得力をもつ言葉。それがコンセプトであり、これが定まっていれば、制作の過程で迷いが生じても判断を取り戻す“核”となる。この視点はデザインに限らず、あらゆる企画・提案・プレゼンテーションにおいて通用する“判断基準”としても機能する。
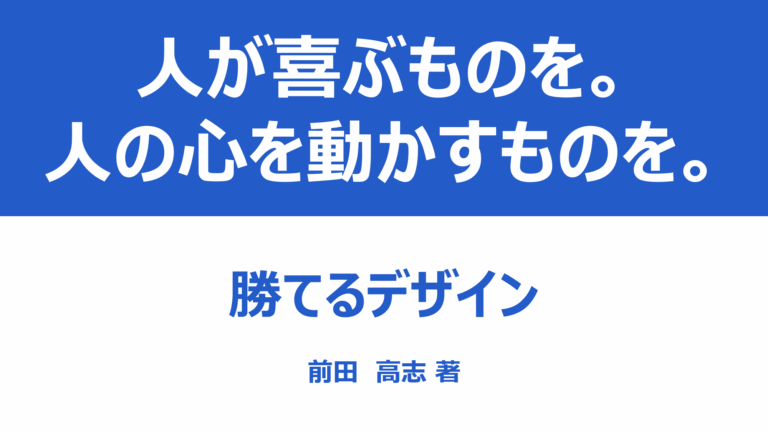
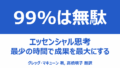
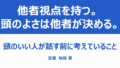
コメント