この本で得られる学び
- 鬼速PDCAとは何か
- 鬼速PDCAを可能にする2つのポイント
鬼速PDCAとは何か
鬼速PDCAとは、PLAN(計画)、DO(実行)、CHECK(検証)、ADJUST(調整)を高速を超える「鬼速」で回し続ける仕事の進め方のモデルである。
- 計画(PLAN)
計画は、PDCAの5割を占める最重要フェーズである。まず、最終的に到達したい山頂を決める。この山頂は、「1年後の今日、あの山の頂に立つ」というくらい明確である必要がある。そのために必要な要素や課題を見つけ、それを解決するための大まかな方向性までを考えることで計画は完了する。 - 実行(DO)
計画の段階で見出した「課題をクリアするための解決策」を複数のアクションに分解し、さらにアクションをタスクに分解する。この時、タスクへの分解をなるべく迅速に実行することが肝要である。具体的なタスクとしてスケジュールを抑えてしまえばやらざるを得なくなり、実行スピードが上がる。計画フェーズで失敗する人が5割なら、実行フェーズで失敗する人は3割。アクションに具体性がないため実行に移せないケースが多い。 - 検証(CHECK)
計画フェーズで考えたルートが最適であるか、頻繁に検証することが重要である。検証をしないと、惰性で現状のアクションを継続してしまうなどの「実行サイクルの無駄うち」が生じてしまう。「もっと効率的な方法はないか?」「他にやるべきことはなにか?」といった、自分の仮説を疑う目線をもって検証を行するとよい。 - 調整(ADJUST)
調整には4種類ある。いずれかの調整を行い、次フェーズのPDCAサイクルにつなげる。- ゴールレベルの調整
現状を検証し、目指す山を変えるという結論に至るケースである。この場合、現在のPDCAを中止し新たなPDCAを回し始めることになる。 - 計画レベルの大幅な調整
検証フェーズにおいて、いままで見えてこなかった課題が顕在化したケースである。この場合、情報収集を一から初めて解決案を検討することになり、PDCAサイクルの速度はいったん遅くなる。 - 解決案や行動レベルの調整
実行サイクルの微修正のことである。大筋の計画は変えずに、やることの優先度を変えるなどの軌道修正をはかる。 - 調整不要
すべてが順調に推移している場合は、調整しないこともある。
- ゴールレベルの調整
鬼速PDCAを可能にする2つのポイント
- PDCAと自信は鶏と卵の関係にあることを意識する
PDCAを回すことで自信が湧き、自信が湧くからPDCAを続けられる。成果が出ない段階でも、ゴールと現状のギャップを把握しながら計画を立てて実行すると「前進している自分」を実感でき、自信につながる。PDCAサイクルを回し続けている限り、ゴールに到達するまで物事を前が前に進む。だからこそ、鬼速PDCAは前進するためのフレームワークであるといえる。 - PDCAを分解する
あらゆるPDCAには、さらにそれを含む上位のPDCAと、それを細分化した下位のPDCAがある。上位PDCAを回すより、効果の大きいと思われる小PDCAに注力して確実に達成していったほうが前に進んでいる感覚が得られて弾みが付く。ゴールが壮大なものであったとしても、それを小さなPDCAに分解していき、個別の課題に落とし込み鬼速でPDCAサイクルを回すことで、加速度的に目標に近づくことができる。
まとめ
著者は、PDCAサイクルはマネジメント手法というよりも「前進を進めるためのフレームワーク」であると説く。本書は学術書ではなく実用書であり「本を読んだ後に実際の行動を促すこと」を前提としている。本記事では紹介していないが、PDCAの各フェーズにおける具体的なステップが記載されている。目指したいゴールに向けて歩みを進めたいすべてのひとにおすすめの一冊である。

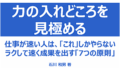
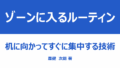
コメント