著者は長年、外資系コンサルタントや脳神経科学の研究者として多様な現場を経験し、「圧倒的に生産性の高い人」に共通する要素を探し続けてきた。その結果、彼らが10倍、20倍と作業が速いわけではなく、何に取り組むべきかを見極める力に優れていると気づく。ビジネスでもサイエンスでも、優れた成果を生むには共通する手法があると確信するに至った。本書では、その核心となる「イシュー」という概念を通して、知的生産活動において何を解くべき問いとするか、そしてその見極めがいかに活動のスピードや質を左右するかを具体的に解説する。
この本で得られる学び
- バリュー=イシュー度×解の質
- イシューとは何か
バリュー=イシュー度 × 解の質
仕事の価値(バリュー)は 「イシュー度 × 解の質」 で決まる。
ここでいう「イシュー度」とは、取り組む課題の重要性や本質度合いを指し、「解の質」はその課題に対する答えの精度や完成度を意味する。多くの人は、解の質、つまり「どれだけ優れた答えを導けるか」だけに注目しがちだが、どれほど完璧な答えを出しても、そもそもイシュー度の低い問題に取り組んでいれば、その仕事の価値は限りなくゼロに近い。反対に、イシュー度の高い問題、すなわち本当に解くべき問いに焦点を合わせることができれば、解の質が多少荒削りでもバリューは大きくなる。
つまり、「何に答えるのか」という問いを見極めることが、すべての出発点だ。多くの人はここを曖昧にしたまま作業を始め、膨大な時間と労力を費やして「努力しても報われない犬の道」に迷い込んでしまう。著者は、その無駄を避けるためにまず イシューからはじめよ と強く訴える。
イシューとは何か
著者はイシューを以下の両方を満たすものと定義している。
A) a matter that is in dispute between two or more parties
2つ以上の集団の間で決着のついていない問題
B) a vital or unsettled matter
根本に関わる、もしくは白黒がはっきりしていない問題
ビジネスや研究においては、数多くの「課題らしきもの」が日々浮上するが、その中で本当に解くべき問いは、100あるうちのせいぜい2つか3つ程度である。
たとえば、食品メーカーで商品が売れないとき、「A商品に魅力がないのか」「販売方法が悪いのか」という問いは重要なイシューになる。なぜなら、どちらの答えを選ぶかで今後の戦略が大きく変わるからだ。しかし、「とりあえず売上が悪いのでSNS広告を強化しよう」というのはイシューではなく、問題の核心を外している可能性が高い。
著者は「良いイシュー」には3つの条件があると述べる。
- 本質的な選択肢である
よいイシューとは、どちらの答えになるかによってその後の方針や研究の方向性に大きな影響を与える選択肢を含むものである。たとえば、コンビニチェーンで「売上が下がっている」場合、まず「店舗数が減っているのか」「1店舗あたりの売上が下がっているのか」を区別する必要がある。前者であれば出店スピードや退店率が課題となり、後者であれば店舗運営方法を見直す必要がある。
気を付けなければならないのが、「なんちゃってイシュー」である。たとえば、長期低迷している飲料ブランドでは「今のブランドを続けるべきか」「新ブランドにリニューアルすべきか」といった問いが挙がるが、そもそも「市場そのものが縮小しているのか」「競合に負けているのか」を明らかにしなければならない。もし市場自体が縮小していれば、ブランド戦略の見直し自体がイシューではなくなる。こうした一見重要に見えるイシューを初期段階で排除することが大切である。
また、「誰にとっても同じように成り立つ」ような問いは、イシューとしての精度が甘い可能性が高い。 - 深い仮説がある
よいイシューには、常識を覆すような深い仮説が求められる。そのためには、まず一般的に信じられていることを列挙し、それを否定したり別の視点で説明できないかを考えることが有効だ。たとえば、「常識の否定(カウンター・イントウイーティブ)」な発想を探るために、分野のエキスパートや現場の人へのインタビューが役立つ。書籍で学ぶ常識よりも、現場の「肌感覚の常識」が覆されたときのほうがインパクトは大きい。
さらに、仮説を強化する方法として「新しい構造で説明する」ことがある。構造化には4つのパターンがある。1つ目は共通性の発見で、「メキシコ建国の人物はメキシコ版の坂本龍馬だ」と例えることで、聞き手は一気に理解が進む。また、「オフィス用プリンタとビル内エアコンの収益構造は同じ」といった共通性の指摘や、「腕と鳥の翼が同じ器官の進化形だ」という生物学的な比較も同様である。2つ目は関係性の発見で、ポールとジョンが親友で同じ行動を取り、ジョンとリッチが対抗しているとわかれば、ポールの行動からリッチの行動も推測できる。科学分野では、異なるホルモンを受け取る複数の脳内レセプター間に関係があるとわかるだけでも理解が進む。このような関係性が10種類ものレセプター間で体系化されれば、その洞察はさらに深まり、実際にこのパターンの研究から多くのノーベル賞が生まれている。3つ目はグルーピングの発見で、市場をセグメントごとに分けることで、商品や競合の現状や将来をより明確に分析できる。最後に4つ目はルールの発見で、複数の現象に普遍的な仕組みや数量的な関係が見出されると、人はそれを理解と洞察として受け止める。 - 答えを出せる
よいイシューは、重要であっても答えが出せない問題ではなく、最終的に明確な答えを導けるものでなければならない。たとえば、商品の値づけ(プライシング)の問題を考えると、3~8社ほどの企業が市場を占める場合、適正な価格設定を分析的に決定する「決まり手」は現在でも存在せず、非常に難しい課題となる。しかし、プレーヤーが2社であれば、ゲーム理論を使って価格戦略の方向性をかなり明確に導くことが可能である。一方で、3社以上になると途端に複雑化し、答えを出すのが困難になる。
イシューを見極める
良いイシューを見極めるには、最初に「本当に答えを出すべき問いは何か」を見つけることが重要だ。課題を闇雲に広げるのではなく、最初の段階で10分の1程度に絞れば、1つの問題に投下できる時間やリソースは10倍以上になる。仮に検証結果が想定と異なっても、進むべき方向に大きな示唆を与える問いに答えることができれば、ビジネスでも研究でも意味のある進歩となる。イシューの効果的な見極め方を
- 専門家と相談する
経験が浅いと、「これは面白い問いだ」と思っても、それが本当に価値のある問いかどうか判断できないことが多い。そこで重要なのが、知識のある人に相談することだ。たとえば、学生やビジネスパーソンでも、気になる専門家を論文や記事、ブログなどで見つけたら、思い切って連絡してみるとよい。研究所やシンクタンクには、相談に乗ってくれる専門家が多い。こうした「知恵袋」になる人物を持つかどうかで、成果の出やすさは大きく変わる。 - 仮説を立て、スタンスを決める
多くの人は「テーマを整理する」段階で止まり、実際の検討に入ってから「イシューは何だっけ」と考え直してしまう。それでは時間が足りない。重要なのは、早い段階で具体的な仮説を立て、「自分はこう考える」とスタンスを決めることだ。「やってみないと分からない」ではなく、最初から仮説を打ち立てて検証する姿勢が成果を左右する。
情報を集めるコツ
イシューを見極めるにあたっての情報収集のコツを3点紹介する。
(1)一次情報に触れる
他人の解釈が入っていない生の情報を集めることが重要だ。二次情報だけに頼ると偏った前提に基づくことになり、誤った判断をしやすい。
(2)基本情報をスキャンする
一次情報に触れつつ、業界や分野の基本的な枠組みを素早く押さえる。ビジネスであれば、マイケル・ポーターの「ファイブ・フォース」(競争関係、新規参入、代替品、顧客、サプライヤー)や技術動向などの基礎知識は必須だ。また、数字(規模、シェア、利益率、変化率など)、問題意識(歴史的背景、業界の常識、過去の試み)、フレームワーク(どの枠組みで問題が整理されているか)をきちんと押さえる。
(3)集めすぎない
情報は多すぎると発想が鈍る。「知り過ぎると新しい視点が生まれない」というのは、コンサルタントが外部視点として重宝される理由でもある。新しいアイデアは、ある程度の疑問や引っかかりが残っている状態から生まれる。だから、情報収集は「知り過ぎる前」で止めるのがコツだ。
まとめ
本書は、仕事や研究において「本当に解くべき問い=イシュー」を見極め、そこに集中することで圧倒的な成果を生むための思考法を徹底的に解説している。「良いイシューとは何か」「どのように仮説を立て、検証し、成果につなげるか」というプロセスを、豊富な事例とともに具体的に示しており、読む者に「考えるとはこういうことか」という強い気づきを与えてくれる。
特に印象的なのは、「考える」と「悩む」の違いに関する著者の視点だ。「悩む」は答えが出ないことを前提とした停滞であり、一方で「考える」は答えを出すために建設的に思考を組み立てる行為であるという指摘は、日々の仕事に直結する示唆を与える。また、著者が強調する「言葉に落とす」力も重要だ。どれだけ鮮やかなイメージやアイデアを持っていても、それを明確な言葉で表現できなければ他者に伝わらず、チームの生産性も上がらない。言葉は人類が長い時間をかけて磨いてきた最も強力な思考ツールであり、これを使いこなすことで思考は一段と明晰になる。
本書は「イシューを見極め、言語化し、実行に移す」ための極意を、著者の経験に裏打ちされた説得力ある言葉で語る。さらに、「悩むより考える」「ビジュアル思考とチームで共有するための言語化」「言葉の持つ力」など、実務や日常の思考法に応用できるエッセンスも散りばめられている。
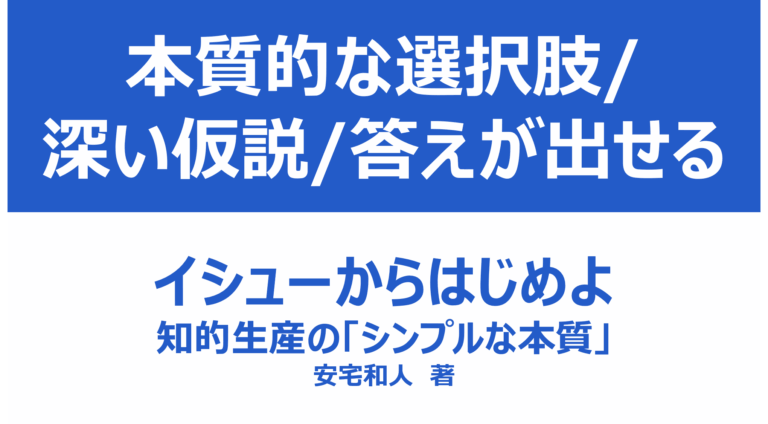
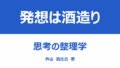
コメント