この本で得られる学び
- なぜ目的ドリブンの思考法が重要なのか?
- 目的ドリブンの思考法の構造:目的⇔目標⇔手段
- 目的を設定するための実践ステップ
なぜ目的ドリブンの思考法が重要なのか?
“何のために”か分からないままにカムシャラに働いても、成果は決して出ない。
そもそも、僕らの仕事は「作業」そのものに意味があるわけではない。その作業を通じて生まれる「価値」の部分にこそ意味はある。議事録の作成も、PCのキーボードをかたかたと叩いて数枚の書面を出力する作業それ自体に本質的な意味はない。大事なのは、「それを人々が読むことで共通認識を醸成できた」という価値の部分にある。
(中略)“目的をつねに意識の主軸に置けば、仕事は成功する”
「目的ドリブンの思考法」より引用
“何を”ではなく”何のために”から始めること。最初の「目的」が明確であれば、そこに目がけて仕事のやり方を最適化し、成果に直結させることができるようになる。目的を頂点として仕事を駆動することが成果創出の原則であり、「目的ドリブン」で考えることのエッセンスはそこにある。
仕事において「成果を出す」とは「目的を達成する」ことと同義である。仕事を通じて目指すべき価値が実現されて、はじめて「成果が出た」と言える。
一方で、その価値に届かなかった仕事は、どれだけ時間をかけようと成果とは言えない。仕事が“終わったか/終わっていないか”ではなく、あくまで、目的に”寄与したか/寄与していないか”に意識を向けるべきである。
「目的」の不在は深刻な問題解決不全をもたらす。目的は「あったほうがよい」のではなく、「明確でなければ成果の創出が叶わなくなる」絶対的な要素である。目的の不在は深刻な問題解決不全をもたらす。目的が存在しない場合の具体的なデメリットは以下の4つである。
①そもそも対処すべき問題が何か分からない
まず、目的がはっきりしていないと、そもそも「何を問題として捉え、解決すべきか」が見えてこない。
たとえば、あなたが新たに立ち上げられた営業部門のリーダーに任命されたとしよう。もしその場で、「じゃあ、あとはよろしく」とだけ言われて任されたら、「よろしくって……何をすればいいの?」と戸惑うはずだ。部署の目的が示されなければ、どの方向に努力すればいいのか、判断のしようがない。
反対に、目的が明確に設定されていれば、その目的と現状とのギャップが問題として浮かび上がり、優先的に対処すべき課題が明確になる。
結果として、本質的でない業務を削ぎ落とし、価値のある取り組みに集中することができる。
②何を優先すべきか・劣後すべきか判断できない
目的があいまいなままだと、どの施策を優先すべきか判断できなくなる。
さきほどの営業部門の例でいえば、「採用を強化して人員を増やす」「新製品を売るためのトレーニングを実施する」など、さまざまな選択肢があるだろう。それぞれ営業成績の向上にはつながりそうだが、どちらを先に取り組むべきか、迷ってしまう。
しかし、仮に「営業生産性の改善」が明確な目的として掲げられていれば、その目的に照らして、すぐに「新製品を売るためのトレーニング」が優先されるべき打ち手だと判断できる。目的があることで、迷いなく優先順位をつけ、スピーディーな意思決定が可能になる。
③的外れなアクションをとってしまう
目的が不明確なままだと、取るべきアクションもズレたものになりやすい。
仮に上の例で「人員を増やす」という打ち手を選んだとする。その場合、「Web採用ページの刷新」といったアクションが出てくるだろう。しかしそれは、「営業生産性を改善する」という目的には直接つながらない可能性が高い。結果として、多くの時間や労力、コストを無駄にしてしまう。
一方で、目的が明確であれば、それに直結する有効なアクションを選びやすくなり、ムダな動きを減らすことができる。
④上司にも部下にも動機づけ・説得ができない
目的があいまいなままだと、チームのメンバーや上司に対して、行動の正当性や必要性をうまく説明できなくなる。これは非常に大きな問題だ。
たとえば、あなたが「営業チームに対するトレーニングを実施したいので、外部講師を呼ぶための予算がほしい」と上司に相談したとする。そのとき、上司はきっと「そのトレーニング、何のためにやるの?」と聞いてくるだろう。その問いに対して「いや、なんとなくスキルアップになりそうで……」という程度の説明しかできなければ、納得してもらえるはずがない。
しかし、目的が明確であればこう言えるはずだ。「当社はこれまでモノ売りが中心でしたが、営業生産性の向上を考えると、サービス領域の売上がボトルネックになっています。その打開策として新サービスの提案力を高める必要があり、そのために外部講師の力が必要なのです」。
このように、目的に紐づけて伝えられれば、説得力が段違いになる。上司や部下の理解と協力を得やすくなり、チームを成果に向けて動かすことができる。結果として、自分ひとりの力に頼る“ワンオペ”状態からも抜け出せる。
目的ドリブンの思考法の構造:目的⇔目標⇔手段
目的を軸にした判断基準を持っていれば、事業や施策の選定に明確な根拠を持てる。そして、その目的が切実なものであればあるほど、その判断には納得感と説得力が生まれる。
一方で、目的があいまいなまま「何をやるか(What)」だけを並べても、腹落ちする意思決定にはつながらない。仮に決めたとしても、どこかモヤモヤを抱えたまま仕事を進めることになり、結果として惰性や思考停止に陥りかねない。意思決定の停滞を招いたり、ただ指示に従うだけの集団を生み出してしまうのだ。
リーダーとして、そうした状況は望ましくない。だからこそ、あらゆる判断や行動の出発点として「何のためにそれを行うのか」という目的を据える必要がある。これは、本書全体を通して最も強く伝えたいメッセージでもある。
Why(目的)–What(目標)–How(手段)の三層ピラミッド構造
これまで見てきたとおり、目的(Why)は仕事の成果を大きく左右する。ただし、目的だけでは成果は生まれない。それを実現するための具体的な行動、つまり「目標(What)」と「手段(How)」がセットでなければ、ただの理想論で終わってしまう。
大切なのは、目的と実行をつなぐ仕組みを理解し、意図的に構築できるようになること。一般に、仕組みが分かれば制御が可能になる。仕事においても、目的達成の構造が分かれば、それをより効率的・効果的に実行できるようになるというわけだ。
その仕組みこそが、「Why–What–How」の三層ピラミッド構造である。具体的には、次のような階層になる。
第一層(Why):達成したい根本的な「目的」
第二層(What):目的を実現するために必要な「目標」
第三層(How):目標を達成するための「手段」
この構造のポイントは、上下双方向で論理が通じている点にある。上から下に見れば、「目的をどうやって達成するか」という流れでつながる。下から上に見れば、「それは何のための手段・目標なのか」と問い直すことができる。
つまり、「何のために(Why)」「何をするか(What)」「どうやってやるか(How)」という三つの層が一貫して結びついていることで、行動の整合性が保たれるのだ。
さらに、目的が抽象的である一方で、階層を下るごとに内容が具体化され、現場で制御可能なタスクへと変換される。たとえば、ある手段が適切かどうかは、その上位にある目標の達成に寄与するかで判断できる。そしてその目標も、さらに上の目的と照らし合わせることで有効性を確認できる。
このようにピラミッド構造を明確に意識すれば、最上位の目的から現場のアクションまでが一本の線でつながり、実行がより意味あるものへと変わっていく。結果として、抽象的だった目的も、実際に「制御できる」形で組織の行動に落とし込めるのだ。
この仕組みを理解し、使いこなせるようになること。それが、先行きが不透明で変化の激しいVUCAの時代において、僕たちが成果を出すために必要な思考のフレームワークである。
目的を設定するための実践ステップ
「目的は何か?」という問いに自分自身で答えようとするとき、どのようにその答えを導き出せばよいだろうか。これは、リーダーが担う最も本質的な仕事——すなわち「目的を定めること」に直結している。本書では、そのための具体的な方法論を示している。
目的を設定するには、まず以下の2つのステップを踏む必要がある。
1.目的を設定するための材料をそろえる
- ポジション(自分の立場)
- 時間軸(どのタイムスパンを想定するか)
- 使命と意思(なぜ自分がそれをやるのか)
2.目的設定の材料(ポジション、時間軸、使命と意志)を統合し、目的を言語化する
以下、詳細を解説する。
1.目的を設定するための材料をそろえる
ポジション —— 組織の中での「ちょうどいいレベル」を見極める
組織では、CEOが掲げる最上位の目的を頂点に、各部門がその実現に向けた目標や手段を担う形で、目的が階層化されている。このピラミッド型の構造は偶然ではなく、組織が「問題解決機構」として機能するための合理的な構造だ。
目的を適切に設定するには、自分の立場に応じた「ちょうどいいレベル」の目的を意識する必要がある。抽象度が高すぎると現場で機能しないし、細かすぎても組織的な意義を失う。したがって、リーダーには以下の2つの視座が求められる:
- 俯瞰的な視座:上位目的が何を目指しているかを理解する
- 接続的な視座:下位にあたるチームメンバーに何を求めるかを考える
こうした視座を持つことで、上位の目的と現場の活動を一貫させる橋渡しが可能になる。現場と経営の間には、しばしば目的の「断絶」が生じる。上位目的は抽象的であるがゆえに、そのままでは現場で理解・実行されにくい。
だからこそ、リーダーには「翻訳者」としての役割が求められる。これは単なる言い換えではなく、経営の意図を深く咀嚼し、自分自身の言葉で再構築してチームに伝えるという行為だ。その翻訳を通じて、組織全体に一貫性のある目的が浸透していく。
時間軸 —— 目的のスケールを決める「もう一つの軸」
目的を考えるとき、「空間軸」──つまり、自分のポジションに即した役割や立場──に加え、もう一つの重要な軸がある。それが「時間軸」である。
横に一本の矢印を引き、その上に点を打って期間を区切っていく。これが「時間軸」である。この軸をどのくらいの長さで設定するかによって、目的の広がりやスケールは大きく変わってくる。
たとえば、1~2週間程度の短期を想定するなら、「競合のシェア分析を終える」「次回定例会に向けて課題と対応策をまとめる」といった、実務的で具体的な目的になる。一方、3~5年という中長期を見据えるなら、「既存事業の選択と集中を進める」「新たな事業の柱を構築する」といった、事業の方向性そのものを左右するような大きな目的が立ち上がってくる。
つまり、目的のスケールは、設定する時間軸によって決まるのだ。
このように目的の射程を見極めるには、あらかじめ自分の中に「時間軸の感覚」を持っておくとよい。具体的には以下の5つの区分をベースラインとすると考えやすくなる:
- 超長期(10年〜)
- 長期(3〜5年)
- 中期(1〜3年)
- 短期(1ヶ月〜半年)
- 直近(週次・日次)
では、どの時間軸で目的を設定するのが適切なのか?──その答えもやはり「ポジション」にある。
たとえば、現場を担う中位層(課長・係長クラス)であれば、企業ビジョンのような10年後の未来を思索することが優先されるわけではない。今まず向き合うべきは、この先数ヶ月〜1年で果たすべき現実的な課題であり、あるいは来週・再来週に対応すべき業務上のテーマであるべきだ。
もちろん、「視座を高く持つな」と言いたいわけではない。将来の展望や組織全体の方向性に対して俯瞰的な理解を持つことは、組織としての一貫性を生み、あなた自身の成長にも大いに資するだろう。しかし、まず大切なのは、今のあなたのポジションでしか担えない目的を明確にすることだ。
その目的を一つひとつ果たす中で、いずれ自分自身の視座も広がり、今の時間軸では収まりきらないスケールの目的が自然と姿を現すようになる。そして、周囲もまたあなたが新たな目的を担うことを期待するだろう。
だから、無理に背伸びをして「遠い未来のビジョン」を掲げる必要はない。今この時、自分の立場で果たすべき役割を見極め、それにふさわしい時間軸で目的を設定する──それが、組織における目的設定の出発点なのだ。
使命(すべき)と意志(したい) —— 目的を生み出す「内なる力」
これまでに「空間軸(ポジション)」と「時間軸(射程)」という2つの視点から、目的を設定するための“枠組み”を整理してきた。しかし、それだけでは十分ではない。枠組みがあっても、そこに自然と目的が湧き上がってくるわけではないからだ。では、目的はどこから生まれてくるのか?
それには、自らの内にある“エネルギー”、つまり目的を形づくる「力の源泉」が必要になる。
「目的(Objective)」とは、単なる客観的なゴールではない。それは、「何を意図して、なぜそこを目指すのか」という主体の意思を伴ってはじめて意味を持つ。たとえば、観光地の情報をいくら並べても、「ここに行きたい」という気持ちがなければ、行き先は決まらないのと同じだ。
目的は、あなた自身の“思い”がなければ立ち上がらない。
では、その「思い」の源には何があるのか?
それが次の2つの力だ。
①「すべき」という使命感
ひとつは、「○○すべきだ」と思う気持ち、つまり使命である。
たとえば、目の前で子どもが川で溺れていたら、私たちは自然と「助けねば」という気持ちになる。これは「誰かが困っている」「あるべき姿から逸れている」と感じたときに生まれる感情だ。
ビジネスでも同じように、たとえば部門間の対立を目の当たりにして、「開発と営業が連携すべきだ」と考える。あるいは、既存顧客ばかりに依存する営業の姿を見て、「新規顧客の開拓を進めるべきだ」と確信する。これらはいずれも、問題や課題に対して“あるべき姿”を求める感覚、つまり使命から湧き出てくる目的である。
この「使命」に根ざした目的には、人を動かす強い力がある。逆に、使命感の伴わない目的は、形だけ整っていても空疎で、人の共感も行動も生み出さない。
②「したい」という意志
もうひとつの源泉は、「○○したい」「ぜひ取り組みたい」という意志だ。
使命が“あるべき姿”という価値観からくるものだとすれば、意志は内発的な意欲や好奇心から生まれる。「こうしたら面白い」「自分が成し遂げたい」という気持ちだ。
たとえば、「モノ売りから脱却して、プラットフォームビジネスに挑戦したい」「自社工場を世界に誇れるようなスマートファクトリーに変えたい」「デジタル技術で営業のやり方を刷新したい」──こうした想いは、まさに意志から生まれる目的のかたちだ。
使命が「問題に対する責任感」だとしたら、意志は「未来に対するワクワク感」と言えるかもしれない。どちらも、目的を生み出す強い推進力になる。
「できる/できない」は、いったん脇に置く
目的を考えるとき、多くの人が「自分にはまだ無理かもしれない」「そんなスキルはない」といった “現在の能力”の枠にとらわれがちだ。しかし、それでは目的が「今できること」に制限されてしまい、新しい価値を生み出す可能性は閉ざされてしまう。
目的とは本来、未来に向かって価値を創出する行為である。だからこそ、最初の一歩は「すべき」「したい」というゼロベースの思いから始めなければならない。
能力の話は、そのあとでいい。「どうやって実現するか」は、目的を定めてから考えることだ。
2.目的設定の材料(ポジション、時間軸、使命と意志)を統合し、目的を言語化する
ここまでに、「ポジション」「時間軸」「使命」「意志」という4つの要素を整理してきた。
これらは、目的を定めるための土台、いわば材料である。
では、これらの材料をもとにして、どうすれば最終的な「目的」へと結晶化できるのか?
それに必要なのは、分析(アナリシス)ではなく、総合(シンセシス)の思考である。
問題解決のプロセスでは、しばしば「分析的な思考」が用いられる。つまり、課題を細かく分解し、それぞれの構成要素を見ていくスタイルだ。しかし、「目的を設定する」という行為には、この分析のベクトルを180度転換させる必要がある。大事なのは、「つまるところ、何のためにそれをやるのか?」と問い、バラバラの要素を一つに統合していくこと。それは、「分析」でなく「総合」、断片を統合して本質を導き出すシンセシスの思考だ。
ここで統合すべきは、自分の立ち位置(ポジション)、見据える未来(時間軸)、心の内側から湧く意志や使命、組織内外の課題認識、周囲の期待や環境変化といった複雑な要素たち。それらをひとつの問いで束ねていく。
「結局、自分(あるいは我々)は何を目指すのか?」
その問いに対して、心から納得できる「これだ」と思える一文を導き出すこと。それが目的の言語化であり、このプロセスこそが目的設定の核心である。
裏から目的を見つける“逆の問い”:「もし、その仕事がなくなったら?」
目的を定めるための王道は、「つまるところ何のためか?」という問いを繰り返すことだ。だが、目的を明らかにする方法は、それだけではない。
思考の角度を変え、裏側から目的を浮かび上がらせる問いも有効だ。
それが、次の問いかけである。
「もし、その仕事がなくなったら、何が失われるだろうか?」
この問いを投げかけてみると、その仕事が社会や組織、顧客に対してどんな価値を生み出していたかが明確になる。その価値こそが、あなたの仕事の“存在理由”であり、目的の原型だ。
すべての仕事は、本来「新たな価値を生み出す」ために存在している。
その価値が何かを逆算することで、あなたの目的が輪郭を持って現れてくる。
まとめ
『目的ドリブンの思考法』は、あらゆる仕事において「何のためにやるのか」を起点とした目的思考の重要性を説いた一冊である。核となるのは、「目的→目標→手段」の三層構造を軸に、曖昧な思考や行動を排除し、成果に直結するアクションを選ぶという考え方だ。
目的を言語化する際には、時間軸・ポジション・使命感・意思などをふまえる必要がある点が強調されており、単なる理論で終わらず、実務での活用を前提にしている。
本稿で触れられていない補足として、本書では「認知・判断・行動・予測・学習」という5つの基本動作を、目的志向を支える実行プロセスとして明示している。これは、目的を実際の行動に変換するための汎用的フレームワークであり、日々の業務の中で意思決定の質を高めるための指針となる。

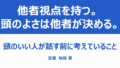
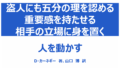
コメント