デール・カーネギーの名著『人を動かす』は、1936年の刊行以来、世界中で読み継がれているロングセラーである。特筆すべきは、表面的なノウハウではなく、人間の根源的な欲求と心理に基づいた普遍的な原則を示している点にある。現代のビジネスや教育、家庭においてもその示唆は色あせていない。
本書の要点のひとつは、「人は論理ではなく、感情によって動かされる」という洞察だ。人間関係において何が最も重要かを問いかけ、誰にでも応用可能な行動原則として体系立てている。今回はその中でも特に重要な「人を動かす三原則」と「人に好かれる三原則」を中心に紹介する。
この本で得られる学び
- 人を動かす三原則
- 人に好かれる六原則
人を動かす三原則
1.盗人にも五分の断りを認める
日常生活で他人と接するとき、つい自分の正しさを主張したくなる瞬間は多い。しかし本書では、それがいかに逆効果かを厳しく指摘している。人は自分の行動に対して、それなりの理屈や正当性を持っている。たとえ社会的には間違ったことをしていても、本人の中では「自分は正しい」という意識があるのだ。
犯罪者は、たいてい、自分の悪事にもっともらしい理屈をつけて正当化し、刑務所に入れられているのは不当だと思い込んでいるものなのである。右に挙げた極悪人たちでさえも、自分が正しいと思い込んでいるとすれば、彼らほどの悪人でない一般の人間は、自分のことを、いったいどう思っているのだろうか。
「人を動かす」より引用
この視点は、家庭でも職場でも応用できる。他人の過ちや欠点を指摘したくなる場面でも、まずは「そういう事情もあるのかもしれない」と受け止める余裕が必要だ。正面から非難すれば、相手は反発するだけで関係は悪化する。
死ぬまで他人に恨まれたい方は、人を辛辣に批評してさえいればよろしい。その批評が当たっていればいるほど、効果はてきめんだ。およそ人を扱う場合には、相手を論理の動物だと思ってはならない。相手は感情の動物であり、しかも偏見に満ち、自尊心と虚栄心によって行動するということをよく心得ておかねばならない。
「人を動かす」より引用
建設的な人間関係を築くには、相手を「説得する」のではなく、「理解しようとする」姿勢が大前提となる。それこそが、感情の壁を溶かす第一歩なのだ。
2.重要感を持たせる
カーネギーは、人間の根源的な欲求として「重要人物でありたい」という感情を強調する。これは、承認欲求や自尊心とも通じる心理であり、人を動かす上で最も強力なスイッチである。
二十世紀の偉大な心理学者ジグムント·フロイトによると、人間のあらゆる行動は、二つの動機から発する–すなわち、性の衝動と、偉くなりたいという願望とである。アメリカの第一流の哲学者であり教育家でもあるジョン·デューイ教授も、同様のことを、少し言葉を換えて言い表わしている。つまり、人間の持つ最も根強い衝動は、“重要人物たらんとする欲求”だというのである。
「人を動かす」より引用
日常のちょっとした会話や態度の中に、相手に「あなたは価値ある存在だ」と感じさせる言葉を差し込むことができれば、人間関係は驚くほどスムーズに回る。ただし、それは単なるお世辞では意味がない。
本書が強調するのは、「誠実な関心」と「率直な評価」だ。上辺だけの称賛ではなく、相手の行動や努力に対して具体的にフィードバックを与えること。それが人の心を本当に動かす鍵となる。
3.人の立場に身を置く
誰かを動かしたいとき、自分の立場や考えを押し付けるのは逆効果だ。相手の関心ごとや価値観を理解し、それに基づいた提案をすることが何よりも重要になる。
だから、人を動かす唯一の方法は、その人の好むものを問題にし、それを手に入れる方法を教えてやることだ。これを忘れては、人を動かすことはおぼつかない。たとえば、自分の息子に煙草を吸わせたくないと思えば、説教はいけない。自分の希望を述べることもいけない。煙草を吸う者は野球の選手になりたくてもなれず、百メートル競走に勝ちたくても勝てないということを説明してやるのだ。
「人を動かす」より引用
この姿勢は、教育やマネジメントにおいて特に重要だ。「どうすれば自分の言いたいことが伝わるか」ではなく、「どうすれば相手の欲求に響くか」を考えるべきなのだ。
「自己主張は人間の重要な欲求の一つである」これは、ウィリアム·ウインターの言葉であるが、我々は、この心理を、仕事に応用することができるはずだ。何か素晴らしいアイディアが浮かんだ場合、そのアイディアを相手に思いつかせるようにしむけ、それを自由に料理させてみてはどうか。相手はそれを自分のものと思い込み、二皿分も平らげるだろう。「まず、相手の心の中に強い欲求を起こさせること。これをやれる人は、万人の支持を得ることに成功し、やれない人は、一人の支持者を得ることにも失敗する」
「人を動かす」より引用
アイデアや提案を相手に“授ける”のではなく、相手が“自分で気づいた”ように見せる工夫。これこそ、相手の自尊心とモチベーションを高める最良の方法だ。
人に好かれる三原則
1.誠実な関心を寄せる
現代社会では、表面的な付き合いが増える一方で、「本当に自分に関心を持ってくれている」と感じられる人間関係は貴重になっている。だからこそ、カーネギーは「誠実な関心を持つこと」の大切さを第一に挙げる。
ウィーンの有名な心理学者アルフレッド·アドラーは、その著書でこう言っているー「他人のことに関心を持たない人は、苦難の人生を歩まねばならず、他人に対しても大きな迷惑をかける。人間のあらゆる失敗はそういう人たちの間から生まれる」
「人を動かす」より引用
この言葉が示すように、「他人への無関心」は単なる性格の傾向ではなく、人生全体に悪影響を及ぼす要素である。他人に関心を持てない人は、共感力に乏しく、信頼も得られない。その結果、孤立し、他人との協働も困難になる。逆に、相手に対する関心は、それだけで人間関係の潤滑油となり、信頼の土台を築くことができる。
では、「誠実な関心」とは具体的にどういうものか? それは、単に相手の話を聞くだけでなく、「どう感じているか」「なぜそう考えたのか」にまで想像を巡らせることである。自分が話しているときに、目を見て頷き、時に質問を挟んでくれる相手には、自然と心を開きたくなるものだ。
こうした態度は、創作の世界にも通じる。カーネギーは、文学の講義で出会った編集者の言葉を通して、この感覚を印象的に語っている。
私は、ニューヨーク大学で短編小説の書き方の講義を受けたことがあるが、その時の講師は一流雑誌の編集長だった。彼は、毎日机の上に積み上げられるたくさんの原稿のうちから、どれを取って読んでも、二、三節目を通せば、その作者が人間を好いているかどうかすぐにわかるという。「作者が人間を好きでないなら、世間の人もまたその人の作品を好まない」これが、彼の言葉である。
「人を動かす」より引用
このエピソードが伝えているのは、言葉の奥にある「人への眼差し」が、文章にも、仕事にも、会話にも必ずにじみ出るということである。誠実な関心は、相手を動かす以前に、自分の在り方として問われるものなのだ。
誠意をもって他者に関わる。その姿勢があってこそ、人は「動かされる」。この原則は、時代が変わっても不変であり、あらゆる人間関係の根幹をなしている。
2.名前を覚える
名前は、その人にとって自分自身の象徴だ。だからこそ名前を呼ばれることは、承認のサインとなる。本書では、その効果をよく活用した人物として、鉄鋼王アンドリュー・カーネギーが登場する。
アンドリュー·カーネギーの成功の秘訣は何か?カーネギーは鉄鋼王と呼ばれているが、本人は製鋼のことなどほとんど知らなかった。鉄鋼王よりもはるかによく鉄鋼のことを知っている数百名の人を使っていたのだ。しかし、彼は人の扱い方を知っていたー–それが、彼を富豪にしたのである。彼は、子供の頃から、人を組織し、統率する才能を示していた。十歳の時には、すでに人間というものは自己の名前に並々ならぬ関心を持っことを発見しており、この発見を利用して他人の協力を得た。
「人を動かす」より引用
人間関係を築く上で、名前を呼ぶことは最も簡単で効果的なアプローチである。名前は単なる記号ではなく、「あなたを大切に思っている」というメッセージなのだ。名前は、当人にとって、最も快い、最も大切な響きを持つ言葉であることを忘れてはならない。
3.関心のありかを見抜く
相手の関心に合わせて話題を選ぶ。それだけで会話の質は劇的に向上する。セオドア・ルーズヴェルトがその好例だ。
セオドア·ルーズヴェルトを訪ねた者は、誰でも彼の博学ぶりに驚かされた。ルーズヴェルトは、相手がカウボーイであろうと義勇騎兵隊員であろうと、あるいはまた、政治屋、外交官、その他誰であろうと、その人に適した話題を豊富に持ちあわせていた。では、どうしてそういう芸当ができたか。種を明かせば簡単だ。ルーズヴェルトは、誰か訪ねてくる人があるとわかれば、その人の特に好きる。そうな問題について、前の晩に遅くまでかかって研究しておいたのである。
「人を動かす」より引用
人と会う前に、相手の興味関心を調べ、そこから会話を始める。このひと手間が、関係を深めるための確かな投資になる。
まとめ
『人を動かす』は、「人間とはどういう生き物か」という深い理解に基づいた、人間関係の哲学書である。相手の心に寄り添い、重要感を与え、誠実な関心を持つ。この三原則を胸に刻むことは、ビジネスでもプライベートでも、あらゆる場面での人間関係を豊かにしてくれる。
そして何より、著者カーネギーの示す原則は、自分が変わることによって、他人を動かすという逆説的なアプローチに他ならない。それこそが、最も確実で、最も誠実な「人を動かす」方法なのだと思う。
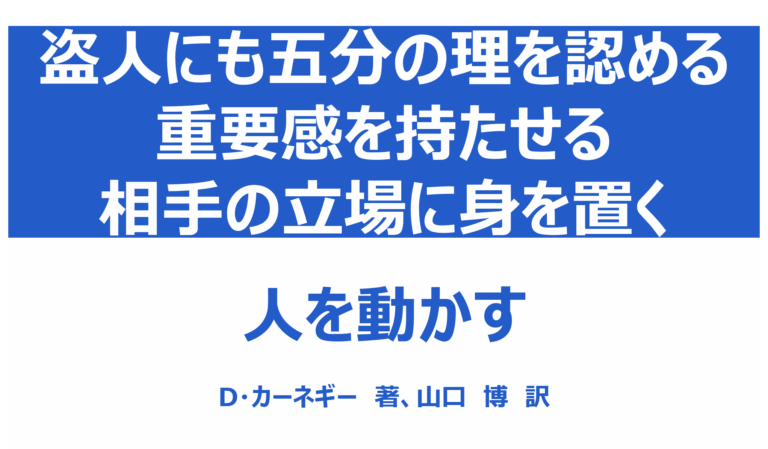
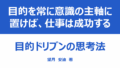
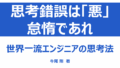
コメント