冒頭、著者は人間の知的能力を「グライダー」と「飛行機」にたとえる。グライダーとは、誰かに牽引されて飛ぶ装置であり、言い換えれば、他者の導きに従って学ぶ、受動的な学習者である。これは学校教育で奨励される能力であり、教師の指導に忠実に従い、既存の知識を効率よく習得する能力に長けている。
一方、飛行機は自らのエンジンで飛び立つ。自分でテーマを見つけ、問いを立て、独自に思考を展開できる人間こそが「飛行機人間」であり、創造性の担い手である。これまでの教育は、グライダー人間の養成には優れていたが、飛行機人間を育てるには不十分であった。
だが、コンピュータという超高性能グライダーが現れた今、人間がただのグライダーであっては、その役割を容易に置き換えられてしまう。これからは、自ら飛ぶ力を持つ飛行機人間が求められる時代である。そこで問われるのは、グライダーに“エンジン”をどう搭載するかということだ。
この本で得られる学び
本書『思考の整理学』は、知識の受け手としての自分から一歩抜け出し、創造的に考える主体となるためにはどうすればよいか、グライダーでもありながら、必要に応じて飛行機にもなれる――そんな“ハイブリッド型”の思考を目指すためにはどうすればよいか、そのヒントを与えてくれる。その内容を大きく二つの観点――「思考を醸すための姿勢」と「思考を動かすための技法」に分けて整理した。
- 思考を醸すための姿勢
- 思考を動かすための技法
思考を醸すための姿勢
発想は酒造りに似ている
著者が示す一つの方法は、論文のテーマ設定を「酒造り」にたとえるアプローチである。
素材を集める
まず、「素材」を集める。文学研究であれば、作品を読むことである。読む中で、感動した箇所や違和感を覚えた部分、よくわからない部分などをピックアップして書き出す。これらが素材となる。ビール造りでいう麦にあたる。
化学反応をおこす
しかし、素材だけでは論文は生まれない。ここに“酵素”が必要となる。酵素とは、素材を化学変化させるきっかけとなる異質なアイディアである。これは、作品そのものから得られるものではない。新聞、雑誌、テレビ、友人との雑談、日常の些細な気づき──そうした「異物」から偶然のように現れるものだ。つまり、発想とは異質なものの化合反応なのである。
寝かせる
素材と酵素をそろえたからといって、すぐに論文が書けるわけではない。ここからが思考の醍醐味であり、著者が特に強調するのが「寝かせる」工程である。すぐに答えを出そうとせず、あえて一度忘れてみる。そうして頭の中でゆっくりと素材と酵素の反応を待つ。こうした「寝かせ」の時間があってこそ、真に独創的なテーマが浮かび上がってくるのだという。
整理とは「うまく忘れる」こと
思考を整理するとは、記憶をただ管理することではない。むしろ、いかに「忘れるか」が思考の質を左右する。著者は、「思考の整理には忘却がもっとも有効である」と断言する。
人間の脳は有限であり、すべての知識を保持し続けることはできない。大事なのは、時間をかけて自然に忘れるのではなく、意識的に忘れていく力を持つことだ。忘却によってこそ、知識は選び抜かれ、深い関心とつながった本質的なものが残っていく。
その過程で有効なのが、著者のいう「つんどく法」である。短期間に大量の情報を集中して読み込み、記憶に焼き付ける。そして、書き出し、必要な部分を選別し、あとは忘れてしまう。忘れようとしても忘れられずに残った知識によって、一人ひとりの知的個性は形作られる。実際、つんどく型の知識人にはスタイルのはっきりした人物が多いと著者は述べている。
知識の習得については学校でも教わるが、知識の整理法、忘却法は誰も教えてくれない。著者はそこに強い警鐘を鳴らす。情報が多すぎる現代において、本当に必要なのは「情報を捨てる技術」なのである。
思考を動かすための技法
書く、話す、声に出す
思考を深め、整理するには、頭の中で黙考するだけでは限界がある。著者は、「書くこと」「話すこと」「声に出すこと」の重要性を繰り返し説いている。
文章として書き出すことで、漠然としていた思考が明瞭なかたちを取り始める。また、書いた内容を音読することで、論理の綻びや不自然な表現が浮かび上がってくる。『平家物語』が優れた構成と表現力を備えているのは、語り継がれる過程で言葉が磨かれ、洗練されてきたからだ。「声を通した思考」は、表現だけでなく思考そのものを純化する力を持っているのである。
加えて、人と話すことにも大きな意味がある。考えがまとまらず、ひとりで悩んでいると、思考は堂々巡りに陥りがちだ。しかし、たとえ雑談のような形であっても誰かに話してみると、自分の考えの輪郭がはっきりと立ち上がってくることがある。ときには、何気ない相槌や共感のひと言が、思考の突破口となることすらある。著者も、書斎にこもって思索を深めるタイプよりも、人に相談を持ちかけ、対話を重ねながら考えるタイプのほうが、むしろ優れた成果を挙げている例が多いと述べている。相談は、思考を刺激し、停滞を打破するための有効な手段であり、孤独な思考の閉塞感を打ち破る強力な助けとなるのだ。
思考に適した「時間」をつくる
思考を深めるには、環境だけでなく「時間」も意識すべきである。著者は、朝、食事前の時間帯がもっとも思考に適していると語る。空腹時の、いわば“頭が澄んでいる”状態でこそ、深い発想が生まれるという。
さらにユニークなのが、著者が実践している「一日に二回朝をつくる」方法だ。昼に仮眠をとり、本格的に目覚めたあとを「もう一つの朝」として再スタートする。このようにして、一日の中に二回、「朝飯前の思考時間」を設けることで、創造的な思考の時間を倍増させることができるというのだ。
現代人は、常に時間に追われているように感じがちだが、実は時間の使い方次第で、自分の中に新しい時間軸をつくり出すことができる。思考には「空白」や「静寂」が不可欠であり、それを意識的につくる工夫が必要だ。
まとめ
本書『思考の整理学』は、知識を蓄えるだけでなく、それをどう整理し、活用し、独自の発想へと昇華させるかを問い直す一冊である。素材と酵素、そして熟成――思考を醸成する過程を丁寧にひもときながら、現代に求められる“飛行機人間”への道を示してくれる。
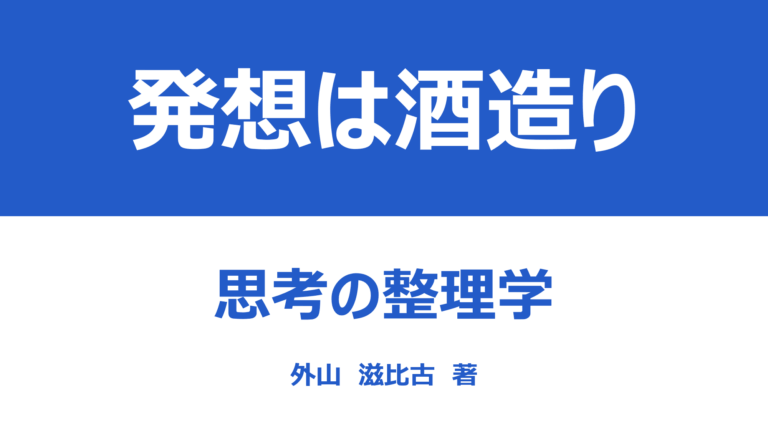
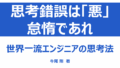
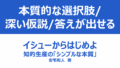
コメント